シャンソンで学ぶフランス語
12月15日と16日に行った面接授業のタイトルです。恒例の年納めという感じで。といっても、まだ2回目ですけれど。シャンソンを5つか6つ選び、聴き取り練習、発音練習、語彙や文法の説明、テクスト分析、文化的な解説、などなど。教室の反応を見ながら、即興で展開する講義。今年のレパートリーは、こんな感じでした。
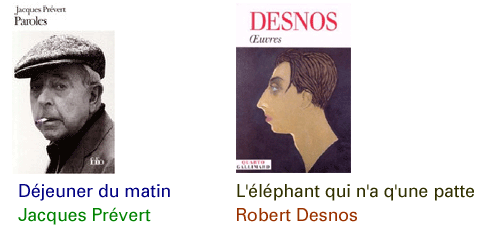

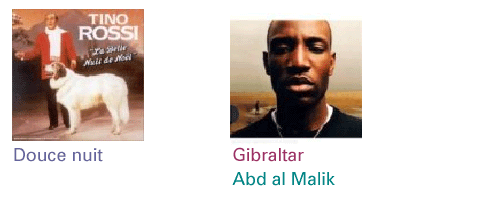
6曲の歌詞は、こちらをご覧ください。(PDF)
この授業、若手の担当講師、笠間直穂子さんとわたしのほかに、ヴァセルマン先生も参加するという贅沢な構成です。もちろんブレインは笠間さん。彼女が惚れこんで、来日したときの通訳から歌詞の翻訳までやってしまったというコンゴ出身の歌手、アブダル・マリックをとりあげたのは、ちょっと冒険でした。なにしろun jeune noir qui pleure un rêve (夢を泣く?)とか、un jeune noir qui meurt sa vie bête(愚かな生活を死ぬ?)とか、作文の時間に書いたら叱られることまちがいなし、というフランス語が並んでいる。ただしアブダル・マリックは大学で哲学・文学を学んだインテリです。Gibraltarの歌詞を緻密に読むと、これが日常のフランス語を反転させながら、意味の乱反射する不思議なポエジーを生みだす仕掛けであることがわかるはず。
せめて人間らしく生きたいと願う人びとが、貧しいアフリカから豊かなヨーロッパをめざし、死の危険を冒してジブラルタル海峡をわたります。しばしば悲劇に終わる密航のドラマを背景に置いて読んでみましょう。ストラスブールの郊外で、犯罪や麻薬に染まって少年時代を過ごした黒人が、イスラームの神秘主義哲学スーフィズムに目覚め、師に教えを乞うために、ヨーロッパからアフリカに向かう。つまりジブラルタル海峡を、反対方向にわたろうという歌です。le merveilleux royaume du Maroc(まばゆいモロッコ王国)に向け、船が進んでゆくところで幕。光にみちた世界への旅立ちという結末は、紋切り型のヨーロッパとアフリカの関係、その明暗の対照を、くるりと逆転させてしまったことになるでしょう。
こんな読解が、出席者たちからの質問や発言をとおし、しだいに形成されていく。さすが「大人たち」の集う教室です。イスラームと対になって、今回はカトリック信仰が話題になりました。
ジャック・プレヴェールと言えば『枯れ葉』―― あの哀愁にみちた優しい言葉の使い手は、じつは過激な反教権主義anticléricalでもありました。ひとことで説明するのは難しいのですが、権威としての宗教に反抗する人間です。カトリックの祈祷や儀式を素材にして、それこそアルフレッド・ジャリそこのけの、破壊的なパロディを演じています。アニメ通の方ならご存じでしょうが、『王と鳥』のメルヘンは、暴君との闘いという緊迫したドラマもはらんでいるわけです。
とりあげたのはDéjeuner du matin ―― お望みなら、ここでも「坊さん嫌い」のエピソードを紹介できるのですが、それはともかく。フランス語を教えておられる若手の先生は、ぜひ、以下のサイトをご覧ください。「お勉強用」の模範的フランス語。これなら、たいていの大学で教材にできる。
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/prevert/dejeuner.htm
エディット・ピアフは映画化されたばかりだし、話し出したらきりがありません。『愛の賛歌』はこちらをどうぞ。http://jp.youtube.com/watch?v=FaEl9Oa7lqQ
その『愛の賛歌』とフランソワーズ・アルディのTant de belles chosesは、どこかで谺を返すようなのです。愛と死を歌うシャンソンだから? むしろ「天国=空」と「この世=地上」という垂直の軸をもつ空間構造がよく似ているからかもしれません。この話をなさったのはヴァセルマン先生(黒板を大きく使って、フランス語と日本語チャンポン)。そうした空間構造は、フランス語の表現そのものに、内包されているのですね。いつもながら、フランスの教育では、テクスト分析の手法が生きている、と感じ入り、ついでに「世界の名作を読む」の通信指導のことを思いだし、ちょっとばかり、うらやましくなりました。
ロベール・デスノスはシュールレアリスムの詩人。1本足の象さんとポンテオ・ピラト(キリストの処刑にかかわったユダヤの総督)の話は、なかなか楽しいのですが、長くなりますので省略。しめくくりは『きよしこの夜』の斉唱でした。
帰り道。木枯らしの吹きすさぶ暗い住宅地を並んで歩きながら、「来年も、いいネタが見つかるかしら」とわたしがつぶやいたら、笠間さん、にっこりして「まだまだ、いくらでもあります!」
